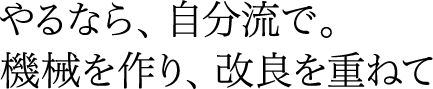
やるなら、自分流で。
機械を作り、改良を重ねて
「装置は、もちろん、自分で作りました。
こういうのは、売り物ではないもんでね。
工場にある機械も、全部、作ったものですよ」
木下商店が箸製造を始めたのは、昭和3年生まれの吉也さんの代から。
小さな工場の歴史は、戦後の日本の道具史そのものだった。
「私の父は、地主の三男坊。戦前、まだ誰もオートバイを持っていない頃から
『インディアン』(アメリカの同名オートバイメーカー製)の1200 なんかを
そこらじゅうで乗り回していてね。
よく親父の後ろに乗せてもらって、いろんなところへ行きました。
それで、私も機械いじりが好きになって、
若い頃は古いオートバイ2、3台集めては、
部品を取って、自分で作って乗っていましたね。
親父は、戦時中は桶を作っていたんです。
空襲があったとき、バケツで水をかけるでしょう?
金物がないから、当時は桶のバケツを使っていて、たくさん必要だった。
戦争が終わった頃、私はまだ学生だったけど、
学校へ行っても、とても授業をやれるような状態じゃなかったでね。
だから、家で桶を作ることを習って、一緒にやりはじめました」
桶作りから箸作りへ移行したのには、
木材の産地として抱えていた、ひとつの懸案が関係していた。
「たとえば、丸太から桶の材料を取るときは、木の内側を使います。
周りの部分は、腐りが早いので桶には使えない。
そうすると、この部分が端材になって、大量に残るんですね。
これを利用して何か作れないものか、と」
同じく木工品の産地である奈良の吉野で、端材を箸に加工していることを聞きつけ、
町ではさっそく職人を招き、技術の習得を試みた。
が、特殊な鉈(なた)を使った箸作りは難しく、なかなか覚えられる人がいない。
そこで、若い頃から手先の器用さで知られていた吉也さんに声がかかったという。
「どうしても、と座り込まれたので、まずやり方を見せてもらった。
でも、手間がかかるし、とてもじゃないがこれでは商売にならんと思いました。
だから言ったんです。『箸はやるけど、私独特のやり方でやりますよ』と」
戦後復興が進み、だんだん豊かさを取り戻す世の中で
求められるのは、気兼ねなく使える割り箸。
そう読んだ吉也さんは、機械いじりで培った知識と技術を生かして
箸を大量生産するための装置を次々と作り出した。
製材する機械。板を切る機械。面取りし、成形し、磨いて仕上げる機械。
やっかいものだった端材が、どんどん箸に姿を変え、流通していった。
割り箸の次は、材料も変え、料亭などで使われる高級箸へ。
作る箸の種類が増えるたび、装置にも新たな工夫を加え、改良が重ねられた。