
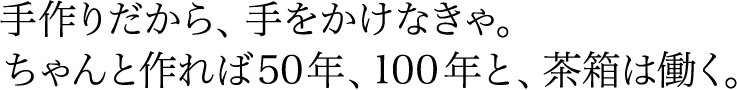
手作りだから、手をかけなきゃ。
ちゃんと作れば50年、100年と、茶箱は働く。
いよいよ、箱を組む。
セメントコートされた32ミリの釘を、金槌で正確に打ち込んでいく。
ここまでのすべての作業を、土屋さんは手仕事で行った。
もとは公務員で、親の仕事を継ぐ気はまったくなかったという。
「15年くらい、焼津の市役所に勤めとった。土木課で、建設関係の仕事。
でも親が年をとって、『あんたにやってもらわにゃ困る』って言うんでね。
私は長男だから、しょうがねえなって。40過ぎてから」
継いだ当初は、茶箱だけでなく、さまざまなものを作っていた。
ジータと呼ばれる、車の輸送用のパレット。ウイスキーの瓶ケース。
今はプラスチックに取って代わられたものは、昔は多くは木で作られており、
木工職人たちは、産業資材の第一線で活躍していた。
「輸出用の軽自動車を載せるやつなんか、10年くらい作ったかな。
いろいろやりました。
茶箱作りのやり方は、子どもの頃から見てましたからね。
職人も、多いときは15人くらい、ここでやっていました」

土屋さんが箱を組み上げたら、
次は外側の仕上げ。
茶箱の角の補強用に、和紙を貼る。
接着に使うのは、小麦から抽出した澱粉で作る生麩糊(しょうふのり)。
伝統的な表具に長く使われてきたほか、
近年では美術品の修復にも使われる天然素材の糊を、
土屋製函所では、生麩を煮て作り、使用している。
和紙は石州産のもの。近年では生産者が減り、値段も高価になったが、
できる限り、昔通りのものを選んで仕入れ、使用しているという。
糊をつけて、一気に伸ばし、端をきれいに折りたたむ。
皺ひとつ寄せない、美しい手仕事が、粛々と施される。

和紙を貼った茶箱は、事務所の一角にうず高く積み上げられ、出荷を待つ。
よく見ると、それぞれの表面の何箇所かに、
小さな正方形の和紙が貼り付けられている。
これは、木の節(枝の跡)を止めるための手当て。
家具作りなどでは、通常、美観の観点から、
節の部分は切り取るか、節のある板自体を採用しないが、
茶箱では、「止めてしまえば、どうってことない」と土屋さん。
簡素な手当てで十分だという、実用品ならではの潔い判断だ。
「節には死に節と生き節がある。
もとの枝が枯れてるやつが、死に節になるんだけど、
放っておくと、ボロボロ抜けてきて、しまいには穴が開くんだよね。
使うには差し支えないけど、まあ、目障りだから紙を貼ってる。
生き節のほうは大丈夫だから、そのまま。
茶箱っていうのはさ、家具とはちょっと違うもんでね。
だから、比べられると困っちゃうんだけど」
外側の目張りができた木箱の内側にトタン板を貼るのは、妻・鈴子さんの役目。
あらかじめ箱型に成型されたトタンの薄板を、慣れた手つきでハンダ付けしていく。
「教えてくれたのは、ブリキ屋さんだった先代。
最初は『えーっ』って思いましたけど。
何だかね、自然と覚えちゃった。フフフ」
保存用の実用品だから、機能を満たしていれば、あとは必要最低限の手間で済ます。
対費用効果を考えても、それは合理的な判断だといえる。
手を抜いているわけではなく、必要な部分に必要な力を注いでいることは、
板干しから製造までの、時間をかけた工程を見ればよくわかる。
「手作りだから、手をかけなきゃ、満足なものはできない。
安い作りをしているものは、すぐに傷んで返品になる。
雑な仕事をすると、あとが大変。
ちゃんと作っていれば、50年、100年は持つ箱だから」
